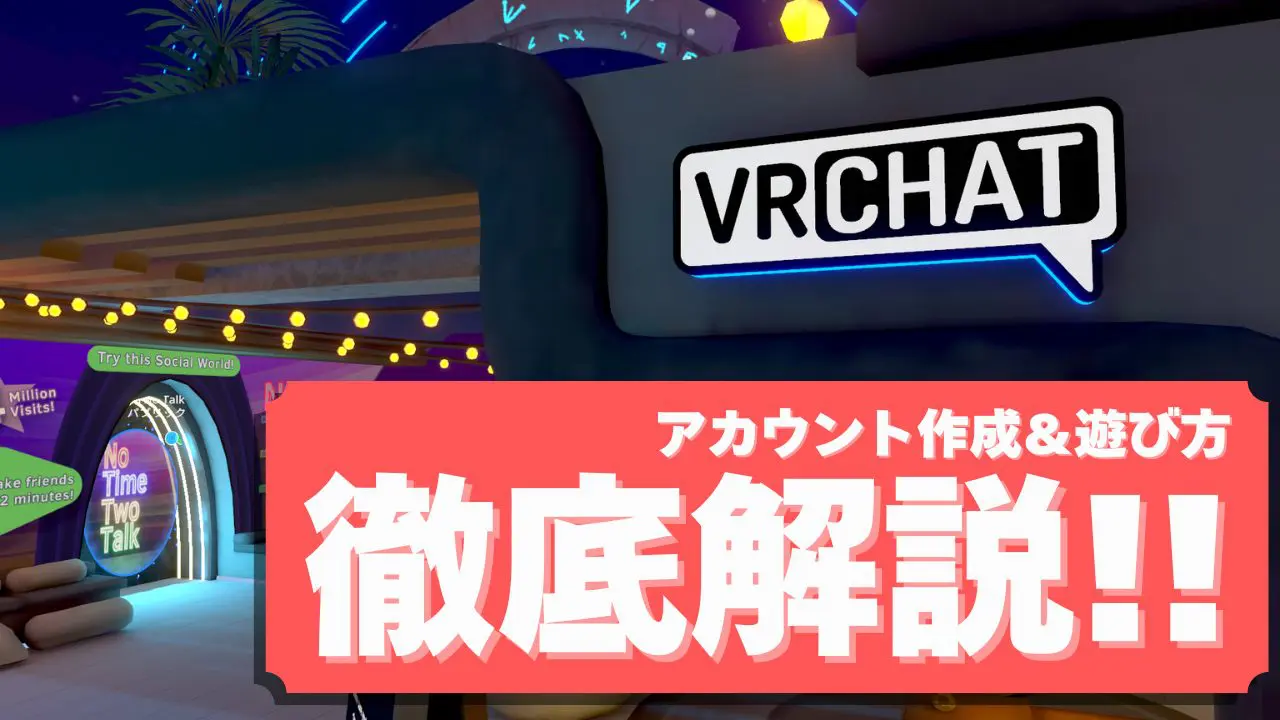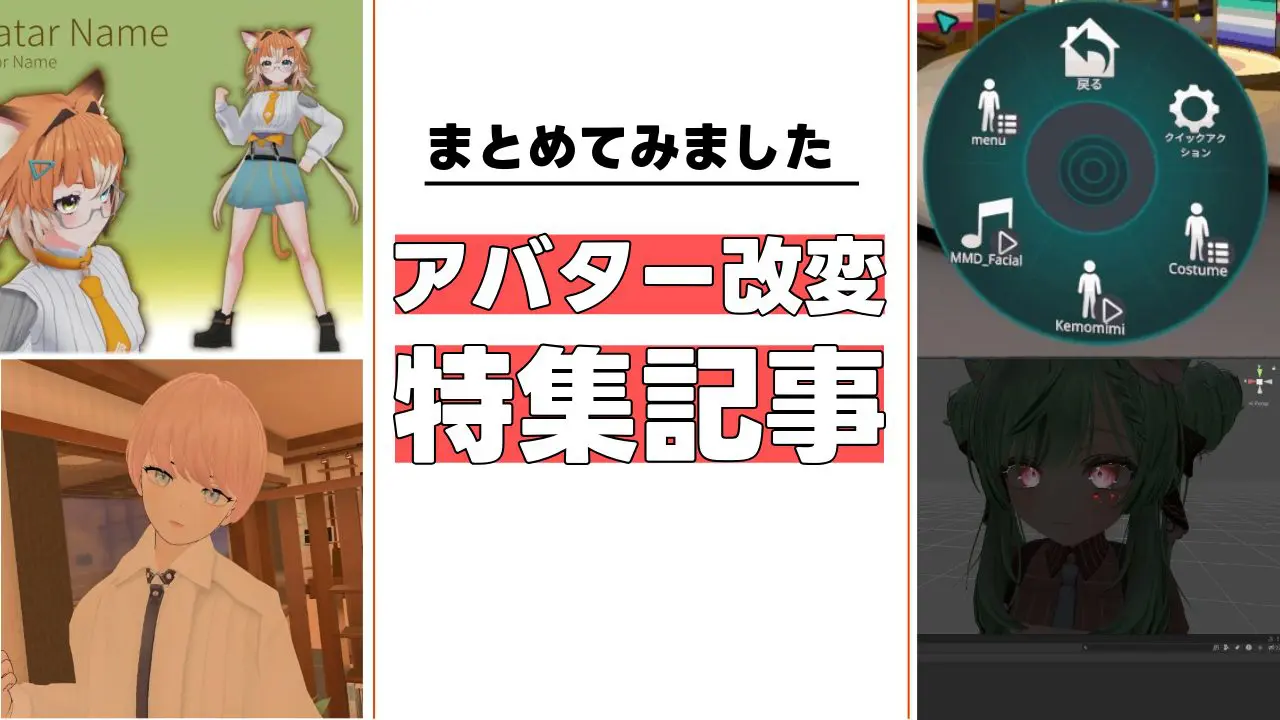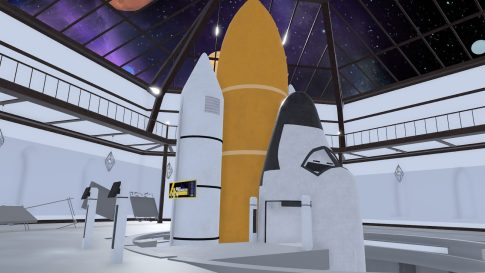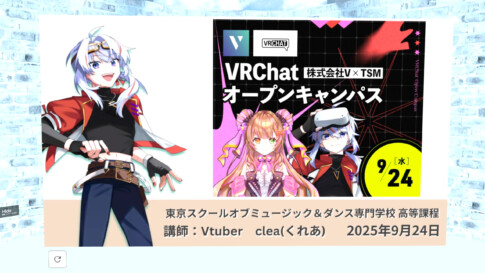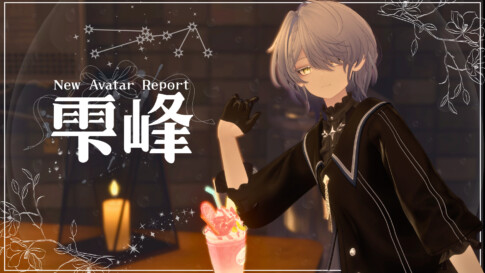VRChatには数多くのユーザーが集まり、交流するイベントが日々開催されています。一方で、イベント運営することの難しさについて実感する人や、直接は関わらずとも遠巻きながら見ている人もいるはず。
その中から、長年、独自のコンセプトで運営してきた音楽イベント『青色クラブ』の主催者である藍上アオイさんと、展示系イベント『PNGミュージアム』の主催者であるmugitarouAKさんをお招きし、イベント運営にまつわるさまざまなことを聞きました。
『青色クラブ』は、毎月第一、第三金曜日の22時から26時まで営業しているVRクラブイベント。地下駐車場を舞台にギミックを除いたフルスクラッチで作られた独自のワールドで開催されています。直近では、英国の映画祭「レインダンス映画祭」のXR部門のオープニングセレモニーやサンリオとのコラボも果たしています。
一方の『PNGミュージアム』は、不定期開催で画像形式のものなら何でも展示OKな展示系イベントです。最新の開催であるPNGミュージアム5では、期間内で掲載された画像の枚数は1200枚。有志による運営をベースにしながらも、掲載の受け入れや関連イベントの実施、クラウドファンディングなど多くのチャレンジを実施しています。
そんな2つのイベントの主催者から、VRChatでイベントを成功させ継続していくためのヒントを、全3回でお届けします。前編である今回は、イベントの立ち上げをどのように行ったか聞きました。

(インタビューアー:柘榴石まおりん)
ゼロからの挑戦とスモールスタート
──コンセプトがないとイベントは始められないと思いますが、お2人はそれぞれどのようにイベントを企画し、立ち上げていったのでしょうか。『青色クラブ』を立ち上げたきっかけを教えてください。
藍上アオイ わたしは元々イベントオーガーナイザーで、10年くらいリアルでイベント運営をずっとやってたんです。スタッフが200人とか250人いた時もあるので、その反動で「次のプロジェクトは1人でやりたい」という気持ちが心のどこかにありました
大人数だと、やはり気を使う部分もありますし、本来やりたいことよりもスタッフのケアや事務的な部分にかなり時間を割かれてしまった実感があって。もちろんそれも楽しい経験でしたし、1人では見えない景色も絶対にあるんですけどね。VRChatなら1 人でもいけるのでは、と思いチャレンジしたのがきっかけです。
──大規模なリアルイベントの経験があったからこその反動、そしてVRChatという新しい場での挑戦、というわけですね。その思いがあった中『青色クラブ』という形になったのは、なぜでしょうか。
藍上アオイ なぜ『青色クラブ』をはじめたかというと、大きく3つの理由があります。まず「地下駐車場」が大好きだったからです。リアルでも地下駐車場でイベントをやりたい気持ちはあったのですが、予算や当時やっていたイベントのコンセプトを考えると難しかった。でも、新規のプロジェクトでVRなら実現できるんじゃないか!と思ったのがそもそものスタートでした。

地下駐車場の話を少し掘り下げると、かつて、渋谷に「Contact(コンタクト)」というクラブがあって、まさに地下駐車場を改造したクラブだったんです。そこがすごく好きでよく通っていました。『青色クラブ』は「Contact(コンタクト)」の影響をとても受けています。
もう1つの理由は、環境としてのクラブが好きだったので、徐々に音の流れてるフロアーに近づいていくような臨場感を再現したかったからそして最後の1つは、物語を考える事が好きなので、イベント自体をひとつの物語にしたい。ナラティブなイベントにしたい、という想いがありました。
主にこの3つの「やりたいこと」を実現するためにスタートした感じです。
──好きを形にしたい、という思いから始まって。そこから具体的にどうイベントの輪郭を作っていったのでしょうか
藍上アオイ まずワールドのプロトタイプを作成しました。3Dモデリングも初めてで、Blenderも使えなかったので、Unityだけでできる範囲で……まずスケールを大きくして、壁を作って、という感じで最初はスタートしました。テクスチャの貼り方なども当時は全然考えていなかったので、アスペクト比がおかしくなって全部伸びちゃって(笑)。とにかく、できることのつぎはぎでスタートしました。
──プロトタイプに着手してから、その最初の告知まで、どれぐらい時間がかかっていましたか?
藍上アオイ 半年ぐらいですかね。多分、最初はスピード感があったと思います。でも最初は、物語をそんなに考える余裕がなくて、ある程度は後付けでやっていました。当時はとにかく「地下駐車場で音楽イベントやるぞ!」みたいな感じでしたね。
──まずは「やってみる」で進めていったわけですね。
藍上アオイ そうですね。完璧を求めず、プロトタイプを作ってみる。VRChatのいいところはフレンドに見てもらうことで、フィードバックを得られたり、自己肯定感を上げられたりするところだと思っています。そうやって日々楽しみながら進められるのがVRChatのメリットですよね。リアルだと箱を借りるのにもお金がかかってしまいますからね。
──プロトタイプを作ってから、実際にイベント開催までにはどういうことをしましたか?
藍上アオイ 正直、最初はそんなにしっかりした計画は立てていませんでした。例えばイベントポスター。今の形になったのも、徐々に「毎回変えていったら面白いかな」と考えて、途中から始めたことです。ウェブサイトも最初はありませんでした。
まずはBlenderとUnityを覚えることで精一杯で、他のことにまで頭が回らなかったですね。今だったら、もっと告知方法とかSNSで画像を投稿してプロモーションしよう、とか思いつきますけど、当時はワールドを公開してイベントをやるってだけでもう個人的にははなまる満点って思ってました。

──告知をSNSで準備して内容を決めればイベントは始められるということですね。ワールドは必ずしも自作する必要はない、と。
藍上アオイ そもそも自分でワールドを作るのは必須ではないですよね。パブリック公開されているワールドでイベントを開催している方もたくさんいます。気になる方は作者さんに許可を取ればいいですし。あと、ワールドのアセットも色々と販売されていますし。
ただ、ポスターやフライヤーのようなビジュアルはあった方がよさそうです。それを作って、最初はフレンドが来てくれれば十分じゃないでしょうか。『青色クラブ』も最初はほぼフレンドだけでした。
問題解決から生まれたコミュニティ
──では、アオイさんのお話が聞けたので、次はmugitarouAKさんにお伺いします。「PNGミュージアム」自体はどういうコンセプトから始まったのか、企画立ち上げの経緯を教えてください。
mugitarouAK 藍上アオイさんの話を聞いていて、すごく対照的な回答になるな、と思っていました。アオイさんは「好き」をベースに始められたと思うのですが、僕はかなり「問題解決型」で始めた側面があります。「これが問題だと思っているから、それをなんとかしたい」という気持ちですね。もちろん「好き」も入っていますが、やろうと思った動機は「問題解決」です。

── 問題解決、ですか。具体的にはどういった問題意識があったのでしょう?
mugitarouAK PNGミュージアムを企画した当時は2021年の初めの頃で、ちょうどコロナウイルスの影響でロックダウンが厳しかった時期でした。僕の周りには絵描きが多くて、コミケのような即売会に出しているようなフレンドも多かったんですが、みんな「締め切りや描く理由が無くて絵を描くモチベーションが無くなってしまった」と話していました。
締め切りがあれば創作意欲が湧くのに、というフレンドが周囲にいたので、皆が創作のモチベーションを失わないように何かイベントの様な形で「締め切り」を提示できないかと考えていました。
──締め切りがあるかどうかで、優先順位が変わって進み具合が変わりますよね。
mugitarouAK 僕がVRChatを始めた2020年当時は、イラストの展示やフォトコンテストといった、いわゆる「締め切り」となるようなイベントが全然ありませんでした。今でこそ「バーチャルフォトグラファー」として活躍されている方もいますが、当時はそういう動きもあまりなく、イラストについて語るイベントやワールドもほとんどありませんでした。
そういった理由もあり、「VRChatに自分の居場所は無いんじゃないか」と感じている絵描きのフレンドもいたんです。このフレンドの発言も僕に何かできないかと考えるきっかけになっていますね。
さらに絵描きのフレンドが、VRChatでの様子を描いたイラストがTwitterの身内のタイムラインの中で閲覧されている事に留まっている様子を見て、「すごくいいイラストなのにもったいないな」と僕自身も感じていました。いいねやリツイートが十数個くらいで、練習作として消費されてタイムラインに流れていくだけ、みたいな。
──当時は、VRChat内では創作を展示する機会すら少なかったんですね。
mugitarouAK せっかくVRChatで創作活動をしているのなら、VRの中で自分の作品が展示できてみんなに見てもらえる場所があれば、きっとイラストを描いている人たちにも光が当たる。コミケのようなイベントがなくなって締め切りという動機がない人にも、新たなイベントを開催することで再び動機を与えられるんじゃないか、と。
その2つの理由が合わさって、「じゃあ、イラスト展示のようなイベントをやってみよう」と考えました。企画のきっかけはそんな感じです。

まずは出展してくれる人への呼びかけから
──「なんとかしたい」というところから企画が始まって、第1回をやるまでにどういうことをしましたか?
mugitarouAK まずは周りのイラストを描いてる友人たちに、「こういうイベントを考えているんだけど、出展したいと思う? 締め切り代わりになるかな?」といった話を持ちかけました。5人くらいに話したら、みんな「いいね、やりたい」という反応だったので、じゃあ本格的にやってみようか、と。
──出展してくれる人の呼びかけ、作品を展示するためには展示してくれる人がいないといけないわけですから最初の一歩ですね。
mugitarouAK その後に考えたのは、「作品を展示するワールド」と「作品の受け入れ方」です。どうやって出展してもらい、それをどうやってUnityに取り込み、どう並べてワールドとしてアップロードするのか。
その際にはQuest対応も必要だから、容量に収めるためにはどうしなければいけないのか……といった要件を、まずバーッと書き出しました。それが多分2番目のステップですね。
──0からフルスクラッチでワールドを作ってイベントを?
mugitarouAK ワールド制作については、そうなります。一度趣味でBlenderを練習して、ゼロからワールドを作った経験があったんです。イベントの形式上、どうしてもフルスクラッチで作る必要があったので、「自分も一度作ったことがあるから、できるかな」と思いました。
──他に広報もしなきゃいけないとなった時に、広報は何をされましたか?
mugitarouAK 広報に関しては、僕も多分、藍上アオイさんとかなり似ているかもしれません。まず大前提として、最初からたくさんの人に来てもらいたいとか、今のような規模で届いてほしいとは全く思っていなかったので、大々的な広報活動はしていません。
初回は自分のTwitterで告知しただけで、あとは周りの友人たちに「募集を開始したから、よかったら出してね」と声をかけるような草の根的な活動をした程度です。他のイベント会場にポスターを飾らせてもらう、といった今のPNGミュージアムがやっているようなことは、当時は全くやっていません。当時は本当に無名の存在だったので。
第1回では、イベント立ち上げのきっかけと思いを語っていただきました。次回、第2回では、それぞれのイベントがどのように成長し、現在の運営スタイルに至ったのか。そして1人運営とチーム運営、それぞれの違いに迫ります。どうぞお楽しみに。