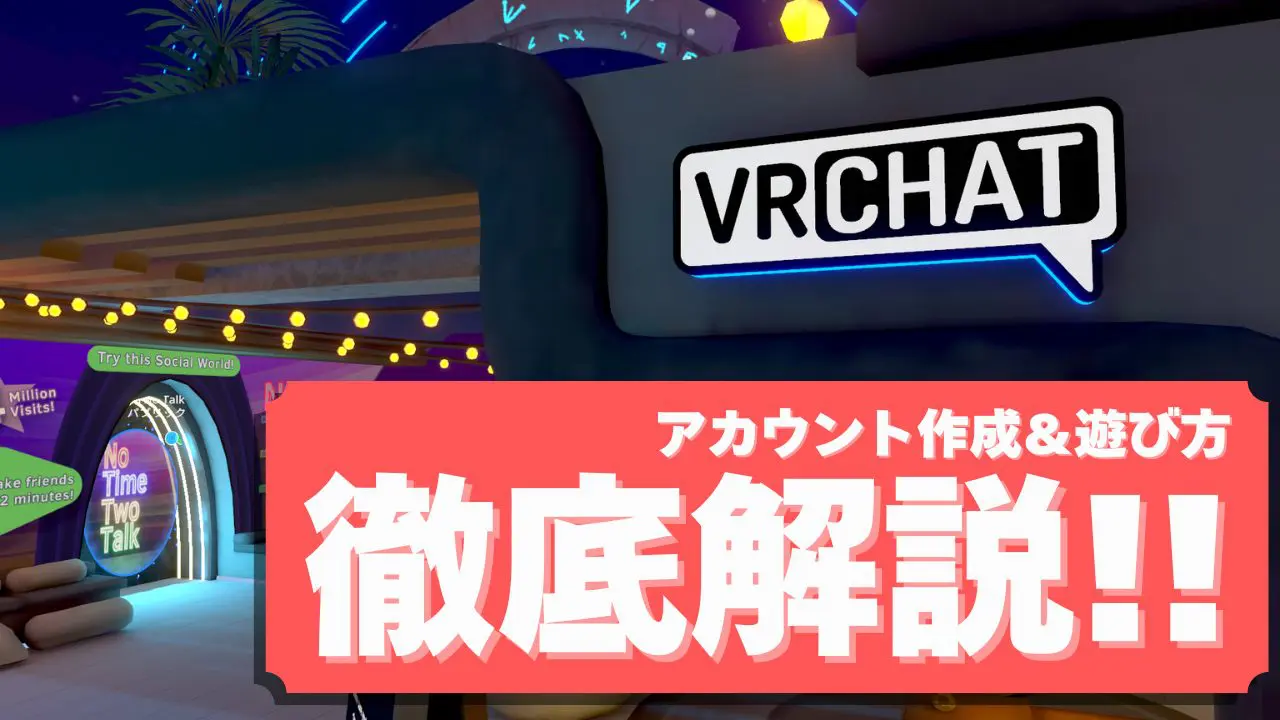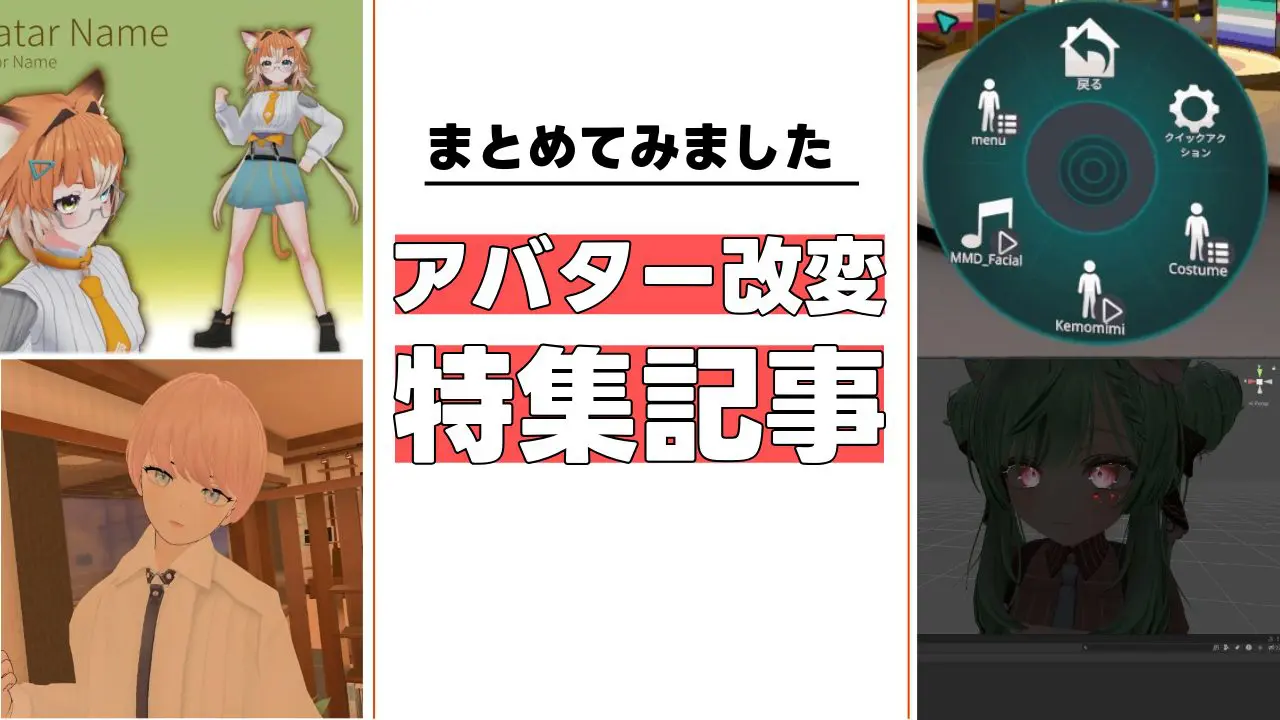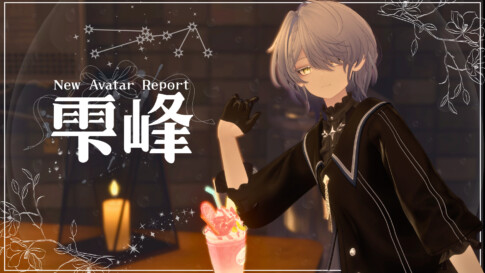音楽系イベント『青色クラブ』と展示系イベント『PNGミュージアム』の主催者である藍上アオイさんとmugitarouAKさんをお招きし、イベントにまつわるさまざまなことを全3回にわたり聞いてきました。
中編の今回は、それぞれのイベントがどのように成長し、現在の運営スタイルが形作られていったのか、その過程と哲学に焦点を当てます。
(インタビューアー:柘榴石まおりん)
1人運営と中立性。青色クラブは「作品」であるスタンス
──運営チームについてきかせてください。アオイさんは今、基本的に1人で運営していますよね?
藍上アオイ サンリオVfesなどの特別なイベントではフレンドさんにお手伝いをお願いしていますが原則1人で運営しています。理由は、自分のペースで好きなようにやりたいからですね。ひとつだけ注釈を入れておきたいのですが、チームワーク自体はとても好きです。青色クラブについては過去の活動のアンチテーゼ的な、内的な課題があるんです。
──アオイさんは、自分の好きを追求してきて、なぜこれだけ受け入れられていると思いますか?
藍上アオイ なぜ多くの人が受けて入れてもらえているか……うーん、難しいのですが、「居場所」として居心地のよさを感じてくださっている方は多いな…とは思っています。。もちろん、流れている音楽や雰囲気も好きでいてくれていると思うのですが、「青色クラブで友達がすごく増えた」と言ってくださる方が多いんです。もう、軽めのコミュニティのようになっているのかもしれません。
自分が気をつけているのは、自分先導でコミュニティは作らない、特定の輪に深入りしすぎない、ということです。中立でいたいので。自分としては、ほどよい距離感で皆さんと付き合っていけてる気がします。
藍上アオイ イベントを続ける上で1番大切なことは「無理をしないこと」だと思っているんですよね。好きなことをやって、それについてきてくれる人がいたらいいね、くらいの気楽さでいます。誰かや何かに合わせず、無理せず、”好き”を好きなようにやっています。それなのに受け入れられているのは…やっぱり居心地の良さがたまたまマッチしたのかなと思ったりしています。
──1人運営の中で、多くの参加者とどう向き合っていますか?コミュニケーションで工夫している点はありますか?
藍上アオイ 最近は参加者が多いので、全員とお話しすることはできなくなってきました。なるべく色々な方とお話ししたいのですが、なかなか難しいですね。
ただ、コミュニケーションコストが低い人だな〜、って思ってほしいので明るく元気にやってるつもりです。特に無理はしていないです。居酒屋やバーやスナック(正確に言うと違うのですが)でのバイトでの接客歴が長いので話すのは好きな方です。
最近の具体的なコミュニケーション工夫ポイントとしては……青色クラブのカラーコードを指定したりオリジナルアイテムを配布してコーデを楽しんだり、定期的に初心者向けの案内ツアーを開いたり、特定の缶ビールを用意してみんなで乾杯しよう、などはやってみたりしています。あと、#AOIROMELTDOWN みたいなハッシュタグを作ったりもしてますね。
──今後、自分以外のスタッフが必要となるフェーズが訪れるとしたら、それはどういう状況であり得ますか?
藍上アオイ 『青色クラブ』の一員として関わってもらうことは今後もないかなと思っています。でも、ギミック制作などで部分的に相談することはあるかもしれません。
──意識して1人でやっている判断をしているわけですね。
藍上アオイ 『青色クラブ』は私の作品づくりなので。イベントのやり方、ワールドのビジュアル面、仕掛け、自分の接客の仕方など、そういうトータルな部分で作品として見てほしいし、課題解決をしてスキルをつけたいと思っています。
──あくまで『青色クラブ』はアオイさんの「作品」である、と。
藍上アオイそうですね。まだまだ…ではありますが、そうでありたいです。『青色クラブ』が、その人の人生にとって、ふと思い返した時に「思い出の地」として残ってくれたらいいな、とよく思います。
よく行った公園とか、人それぞれ思い浮かべるものは違うと思いますが、自分だったらよく行ってた居酒屋とか……その中の一つとして、バーチャルな場所ですけどリアルの場所と横並びになれるような「作品」になれたら嬉しいです。
必要とされているから続けられる
──では、mugitarouAKさんへ『PNGミュージアム』について聞いていければなと思います。実際に第1回目を実施してみての反響や、その後続けていこうと思った理由はなんでしょうか。
mugitarouAK PNGミュージアムの第1回は、出展者数が30人か40人くらいで、来場者数は、当時1週間開催して2000人来たかなぐらいです。
──2021年当時のVRChatユーザー数の規模を考えると、ちゃんと来て欲しい人に来てもらえていた感じがしますね。
mugitarouAK 現在もPNGミュージアムを続けている1番大きな理由は、特に第2回、第3回あたりで会場に来てくださった方々の中に「知らなかった!こんな面白そうなイベントがあるなんて。次回は出したいからぜひやってほしい」と直接言ってもらう機会がすごく多かったことです。
規模が大きくなった今は、なかなか出展者や来場者全員とお話しすることは難しいですが、第3回くらいまではそういった声が多く寄せられました。
自分が最初に思い描いていた、イラスト、漫画、写真といった画像系の作品を自由に提出してみんなで楽しむという場を必要としてくれている人がこれだけいるのなら「自分の理想はみんなも同じように描いていたんだな」と感じました。
みんなが漠然と感じていたモヤモヤしたものに対して、自分が「こういうやり方はどうですか?」と提案したら、受け入れてもらえた。じゃあ、この場所はあった方がいいんじゃないか、と。

──自分の問題提起が、意外とみんな思っていたと。
mugitarouAK それは自分にとっても嬉しいですし、出展してくれる人、見に来てくれる人にとっても嬉しいことです。「続けていくことに価値があるな」と感じ、1回きりのイベントにしない理由になりました。「必要とされている」という感覚があったから続けています。
──「必要とされている」と感じたことが継続の大きな力になったわけですね。
mugitarouAK PNGミュージアム以降に自分が主催しているイベントも、そういった理由が根底にありますね。「今、日本人コミュニティにはこういう課題があると思うから、今とは別の道を示したいな」と思って企画します。
コミュニティを続けていくうえでのどう続けるか、誰を入れていくのか
──mugitarouAKさんは運営をチームですることに関して、どう考えていますか?
mugitarouAK 僕は藍上アオイさんと異なり、一人で運営しているわけではないので、明確にチームの規模がイベントの運営フェーズで変わるんですよ。自分1人でやっていた時期、手伝いたいと言ってくれる人が現れた時期、そして規模が大きくなりすぎて1人では運営が立ち行かなくなった時期。
PNGミュージアムはワールドを作って公開する形式なので、作品を際限なく受け入れられます。どこかで受け入れる作品数に線を引くのか、それともスタッフを増やしてチームとして盛り上げていくのか、という選択を迫られた時に、チームでやるという判断をしたタイミングが第3回でした。
以降は希望に応じてスタッフも増え、できることも増え、アウトプットのクオリティも上がっていきました。組織としても、イベントとしても、そして自分自身としても、フェーズが明確に分かれているので、一言で語るのは難しいかもしれません。

藍上アオイ 質問いいですか?スタッフやりたいって人とか、もう何年もやってますって人がいっぱい増えてくると、mugitarouAKさんだけのPNGミュージアムじゃないわけじゃないですか。それぞれが思い描く「こうあるべきだ」とか「こうなった方がいい」という意見が出てくると思うんですけど、そういったところってどうハンドリングしてるんですか?
mugitarouAK スタッフ間の意見調整については、「ハンドリングできている」と言うとおこがましい気がしています。
最近、PNGミュージアム6の制作を始めるにあたって、みんなで顔合わせして朝まで飲んでいたのですが、その時の話などを振り返って思うのは、結構みんなちゃんと線を引いてくれているということですね。
僕は、藍上アオイさんの言う通り、もう僕だけのPNGミュージアムだとは思っていません。でも、PNGミュージアムのスタッフは、これは僕の思い上がりかもしれませんが、「最終的な判断はもちろんあなたでしょう。PNGミュージアムがどうあってほしいかは、結局mugitarouAKさんが決めないと決まらないよ」というスタンスを取り続けてくれるんです。
「この後PNGミュージアムをどうしていきたいのかはmugitarouAKさんが言ってよ」みたいに。お飾りじゃないぞ、という感じで、常に銃口を向けられているような感覚です(笑)
PNGミュージアムで一番大事にしていることは「みんなの自由を尊重すること」で、それを守ることが自分の役割だと思っています。そうしているからこそ、「どこへ行きたいかは、あなたが決めていいよ」と、みんなに思ってもらえているのかもしれません。
──今チームは何人くらいいるんでしたっけ?
mugitarouAK 現在(インタビュー時)のチーム人数は、ちょっと確認しますね……Discordサーバーのスタッフロールが付いている人は、ジャスト50名ですね。
──これまでの経験で、運営していて何名がベストなチーム人数だと思いますか?
mugitarouAK ベストなチーム人数というのは……いやー、メンバーの能力にもよりますが……最強のプロフェッショナルしかいないなら15人くらいでも回るかもしれませんが、それだと「やりたくないこと」をやらなければいけない人が多くなってしまいます。
あくまで非営利かつ個人主催のイベントなので「やりたくないけどやらなければならないこと」のコストはなるべく分散したい、ということを考えています。なので、そういう人も含めて18〜20人くらいいると、PNGミュージアムくらいの規模であればより個々人が動きやすくなるのではないでしょうか。
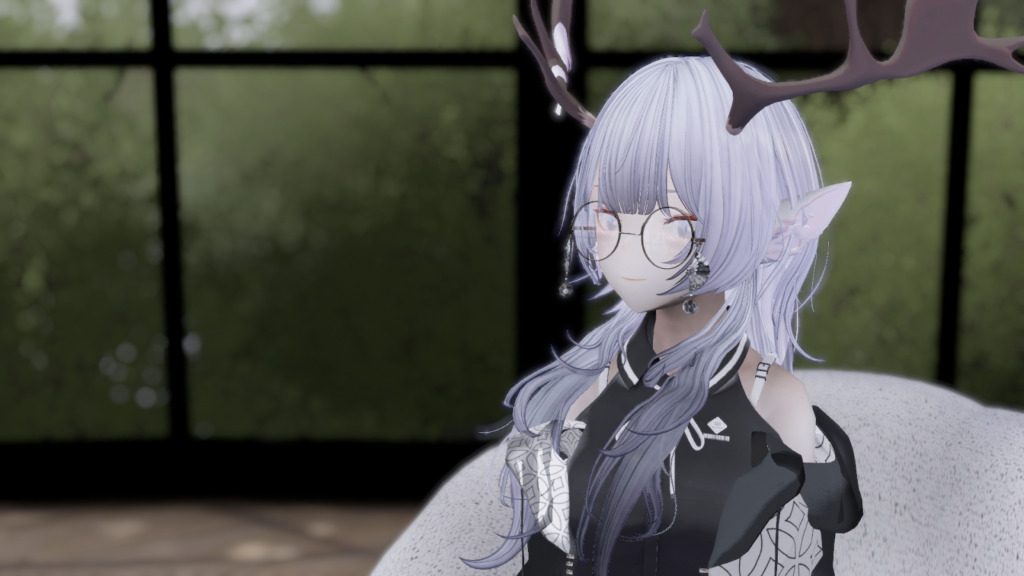
mugitarouAK 稼働できない人が出てきても、受け入れやすくなりますし、緩やかな繋がりを許容するためにもある程度の人数がいた方がいいと思います。長く続けていると、就職、転職、引っ越し、結婚など、色々なライフイベントが出てくるので、「ごめん、今年は全然参加できなかった」と謝られることも当然出てきます。
参加できなくて負い目のある人に対して「いやいや、いいんだよ。イベントはちゃんとうまくいったでしょう」と言うことができて、安心させるためには、ある程度の人数がいて開催自体は確実にできつつ、関わることが難しい時は緩く関われるといった形で、個人の状況に合わせて自由に選べる環境の方がいいです。
だから、20人でも少ないかもしれません。25人くらいいると、特定の誰かに依存するリスクも軽減され、より安定するのではないでしょうか。誰か特定の人に依存しなければならない組織から抜け出せるのではないでしょうか。
──チームを拡大していく上で、スタッフの選考はどのように行っているのでしょうか? 50人ものチームをまとめる上で、何か基準のようなものはありますか?
mugitarouAK スタッフの選考は、僕とVRChat内で直接お話しするようにしています。その際スタッフのインスタンスへの出入りを自由にしているのですが、そこで僕と1対1で話す中で、かなり強烈なフィルターをかけています。応募した人が全員入れるわけではないんですね。
具体的には、応募してくれた方がどういう人なのか、PNGミュージアムの既存メンバーとどれだけ化学反応が起きそうか、といったことを考えています。特に「PNGミュージアムは自由だよ」と言われた時に、どれだけ主体的に活動できそうかは注意して見ていて、指示待ちの人は多分無理なんですよ。
──指示待ち人間かどうかを判断するキラークエスチョンはありますか?
mugitarouAK キラークエスチョンのようなものではなく、その方の雰囲気や考え方、反応を見ています。質問として大体聞くのは、「VRChatはいつ始めたんですか?」「どんなことをしていたんですか?」「なぜそれをやったんですか?」といった内容です。
あと、僕は最初に「僕への質問には基本的にNGなしで答えます。その代わりあなたも僕のことを信じて、今思っていることを正直に話してください。お互いにとって良くないですから」と伝えるようにしています。
その上で「なぜやりたいの?」「何をしたいと思っているんですか?」と聞きながら、周りで他のスタッフが「次はこんなことやりたいよね!」と話し始めた時に、それに圧倒されてしまわないか、乗ってこれるかどうか、といった様子などを見て判断することもあります。
既存のスタッフに対して「私なんか……」って萎縮して喋らなくなってしまう人は、多分入ってもしんどいと思うので、大体お断りします。スタッフたちが話しているその場にスッと入れる人は、きっとうまくやれるんだろうなと思って、僕は話している様子を黙って見ていることが多いですね。
──そういう前提で集まっているチームだと、不和はそんなにないのかなと思いますが、今までチーム内で激しい対立とかありましたか?
mugitarouAK チーム内の対立についてですが、ものすごく激しい対立というのはありません。ただ、前回少し発生したのは……PNGミュージアムの歴史が長くなってきたことで、過去の議論の経緯や「こういう判断で、あえてやっていないんだよね」といったことが、蓄積されてきています。前回、新しく「こんなことをやりたい」と企画した人たちが、ちょうどその回から参加したメンバーだったんです。
そして、議論をややクローズドな形で進め始めてしまった。Discordのオープンな場所ではなく、DMベースや、他のスタッフがいないVRChatでの会話やスタッフへの確認が不十分なまま進めてしまったんですね。
気づいた時には、長く関わっているスタッフにその話がまったく伝わっていませんでした。その部分を丁寧に、段階を踏んで進めたいと思っていた古参のスタッフから「いやいや、待ってよ」というストップがかかってしまったわけです。
そこで、ちゃんと企画した人たちと問題に対してずっと考えてきたスタッフを集めて、みんなで話し合いの場を設けました。話し合い自体は大きく揉めることも無く、お互いに事情を説明して、今後の対応について冷静に話し合うことができました。こういったことはイベントが長く続けば、絶対1、2回は発生する、避けては通れない話だったと思うので。みんな大人な対応で、大事にしないでくれてよかったです。
中編では、1人運営とチーム運営、それぞれの運営スタイルと成長の過程を伺いました。
最終回となる後編では、これからイベントを始めたい人への具体的なアドバイス、イベント運営におけるメンタルケア、そして2人のクリエイターが共通して持つ「コンセプトの強度」について掘り下げます。次回もお楽しみに。