VRChatにはワールドが多くあり、その中にはクオリティの高いワールドも存在します。メディアとしては、高クオリティのワールドやユニークなワールドを記事にするのは仕事としてやるべきことです。
しかし、記事にするときにとある悩みが出てきます。
もちろん世に公開する記事は、自分ができることを100%やったものです。一方で、知見がある人がワールドを見たら思いのよらぬ視点が映っているのではないだろうかと考えてしまいます。
しかし、このまま「たられば」で続いてしまうのも気が晴れないものです。
今回はワールド「VR宇宙博物館コスモリア」を制作したことで知られている天文仮想研究所(以下、VSP)の所属メンバーと宇宙に関するワールドに行ってみました。
結論から言うと、同じワールドにいるはずなのに見えている世界が別物でした。
今回巡るメンバーは以下の通りです。


無重力ひとつで話が広がっていく「Generations – Project RAMA 」

遠心力を使って重力を再現しているので、中央に近づくほど重力が弱まり、外側に行くほど強くなる感じです。

エレベーターで位置が変わっているから重力も変わっていますね。でんじろう先生がやっている、石にひもを付けてぐるぐる回す実験と同じ理屈ですか?

人工重力の原理は回っている石が私達になるようなものですね。


恒星間宇宙船の発想自体はいろいろなSFで出てきますよね。現実では開発・研究はどこまで進んでいるのでしょうか?

人間が住めるスペースコロニーすら出来ていないのに、恒星間宇宙船は夢のまた夢ですよ。

環境を独立空間に保存するバイオスフィアの試みは、大変ですよね……

1980年代にアメリカで行われたバイオスフィア2実験では、ドーム内に植物、動物、人間を入れて、外から水や空気を取り入れずに環境を維持する試みが行われました。2年間実験を行っていて、上手くいっていたのですが……
実験終了後、途中で二酸化炭素の濃度が上がってしまい、外部から空気を交換していたことが判明し、実験は失敗に終わりました。

炭酸ガスを1番吸収するのは海という説があります。海が炭酸ガスを吸収することで、植物プランクトンを活性化する流れが必要だと考えられています。なので、木がたくさん並べられていますが、木だけだと炭酸ガスの吸収が難しく立ち行かなくなるのかもしれません。

ガンダムなどのいろいろ創作物で描写はありますが、川はあれど海はないですよね。

人間が住む環境にするためには、海と陸地の割合を3:7にしないといけないのかなと思っています。それに深さもないといけないですね。地球は奇跡の惑星とも言われますが、むしろ逆とも言えます。人間は海と陸地の割合が3:7の環境で生きていて、適応しているのが正しいのかなと考えられています。

人間が宇宙進出するとなると、割合を意識した環境を作らないといけないわけですか。

窓がないですね。宇宙船としては理にかなっているデザインです。


太陽系外に出るとしたら、窓はあっても使えないんじゃないかな。

恒星間宇宙船だとしたら、自己完結しないといけないし、熱が逃げて危ないですよ。

コロニーが舞台の創作物だと、窓が割れて危ないみたいなのはよくあるイメージです。

ネームプレートが斜めになっていることを考えると本当に移動していることなのかな……筒の形になっているワールドを作るときは、重力の設定があるので普通はアバター側を固定して世界を動かしていくような作りになっています。ただこのワールドは、逆になっていますね。

入口を原点とすると、歩いてきた距離がそのままネームプレートのズレになっているでしょうね。

もしかしたら無重力のシステムと連動しているかもしれませんね。無重力時にネームプレートが連動して動いていました。

エレベーターなどの挙動を考えるとワールド全体におそらく重力のパラメーターみたいな設定をしているんじゃないですかね。見たことのない謎技術ですよ……!

考えてみたら無重力空間を再現するのにも、VRChatのワールドだとギミックが必要になるわけですか。仮想でも世界を作るなら物理を学ばないとダメなやつだ……
実際に宇宙で資材を調達するなら……?「Far Citizen ˸ Elite Mining」


「Far Citizen ˸ Elite Mining」は小惑星で採掘を楽しめるワールドですね。ワールドに入るとカフェが併設されている拠点に出ますね。それにしても窓の外を見たんですけども、回転が早くないですか……?

めちゃくちゃ酔いやすいですね。NASAの研究によると、遠心力を使った人工重力は1分間に2〜3回転が一般の人が耐えられる限度なんですね。

窓は作るべきではないですね。

めっちゃくちゃ酔いますし、先ほど話していた安全面の話もありますからね。

速度が速すぎると、窓がなくても酔いが発生するらしいです。

人工重力はあると便利なので、宇宙船の半径を大きくして少ない回転数で発生できるようにしたいところなんですよね。

なので、小さい宇宙船とかになると回転数が多く必要になるので人工重力の実現が難しいです。面白いのが、VRでも同じような現象が起きました。VSPにも所属していて宇宙系のワールドを数多く手掛けているS_ASAGIRIさんがテスト用に人工重力場を作ったのですが、現実と同じように酔いました。

VRでも現実の物理と同様の現象が起きるのですか。

三半規管と視覚の誤差なので、れっきとした「宇宙酔い」です。

これは小惑星から資源を採取するマイニングカートですね。

率直な疑問なのですが、建設するための技術的な問題がないと仮定して、宇宙船やコロニーのような建造物や生存に必要な素材はどうやって調達するのでしょうか。

どのように条件を設定するかによりますが、例えば宇宙空間で水を調達するのは大変です。おそらく1番簡単に取れるのは彗星からなのですが、安定しません。金属で考えると、効率を考慮しないのであれば鉄やニッケルは小惑星からそこそこ取れると思います。
1番難しいのは貴金属だと思います。貴金属が取れるのは、地球のような重力が一定ある場所で、かつ中心部分にある場所になります。なので、他の星に行っても集積されている量が期待できないですよね。ただ一方で、地球の場合は中心部分にあるけども他の星なら露出しているのではないかという可能性もあります。

ガンダムで実弾兵器以外にもビーム兵器があるのは、わりと理にかなっている話なのかもしれない……

そもそも地球由来の鉱物は、地球の水や熱の変性を受けてできているものが多いです。溶けて集まった結果、鉱物になることを考えると、私としては人類に都合よく集積する可能性は低いと考えています。

地球はあくまでも地球の環境による集まり方をしているのであれば、他の惑星に行ってもセオリーが通じないわけですよね。そうなると宇宙開拓して資源調達するのは、闇鍋のガチャを引くようなものなのでは……?

気づいてしまいましたか……宇宙空間に行って何を欲しがるかによって変わってくる話ではあります。例えば、木星に行ってヘリウムを取ってくるのは実現性があります。木星は地球の11倍の直径があって、ほとんど水素とヘリウムで構成されているんですよね。だから、地球に比べたら取り放題みたいなものです。

ガンダムで木星からヘリウム採掘をする話があるのですが、木星は放射線が人間にとって致死量あるので実際にやるのは難しいと思います。

無人機で採掘する手はどうなんでしょうか。

無人機でもシールドを手厚くしないと電子機器が焼けてしまって使い物にならないと思いますね。
意外と快適な宇宙暮らし事情「Scarlet Monarch MKII」


「Scarlet Monarch MKII」は居住区のようなワールドですね。

メニュー画面を触っていると外の景色が変わりますね。

ずっと同じ宇宙空間だと狂いそうになるから、変えたいと思ったんですかね。

世代を重ねた結果、宇宙進出後に育った子供による事故が起きそうで、なんだか嫌な予感がしますね……

そこは流石に誤操作が起きても事故にならないような設計なんじゃないですかね。

わりと衝撃的なキューブみたいな食べ物がありますね。3Dプリンターで出している感じですね。

キューブ状なのも管理しやすくするためですか。ところで、実際の宇宙食はどのような感じで作られているのでしょうか。

今はわりと国際宇宙ステーションあたりの距離であれば、結構持ち込めますね。日本のHTVで輸送された生鮮食品は4週間以上保つようになっているとのことですよ。

昔の歯磨き粉のような宇宙食をイメージする人がいるかもしれませんが、飛行機の機内食みたいなものもあるんですよね。地球の料理と違って、無重力空間で食べやすいようにしないといけません。要は無重力空間だと料理が飛び散ってしまうわけです。
地球と同じようにナイフとフォークで食べるような食べ方は、とろみがないと難しいですね。あるいは皿に料理を固定する方法もあります。難しい場合は、袋に詰めて飛び散らないようにするといった感じです。

宇宙食の制約は、食材というよりも食べ方のほうが大きいわけですか。

宇宙食といえば、日清が宇宙食ラーメンとか出していますよね。

今ざっと調べたら宇宙日本食認証を取得したニュースとして出ています。


以前、宇宙空間でレタスを育てるといった話が出ていましたよね。

国際宇宙ステーション(ISS)で生野菜を栽培した話がありますね。

収穫量として微々たる量だと思いますが……

でも、可能ではあると。居住区で思うのですが、宇宙空間に人が住んだら時間の基準はどうなるんですかね。宇宙ステーションの場合はどのようにしていますか?

イギリスを基準とした24時間で動いていますね。

月の標準時刻を作ったほうが良くない?みたいな議論は出ていますよね。

NASAのグループ内ではあるものの火星に関しては基準となる時刻は作られていますね

太陽電池やカメラを使う都合で、火星の昼間に動きたいわけなんですよね。なので、火星探査のグループは、火星を基準とした時間で動いています。

ただ火星って1日が25時間弱で少しズレているから、地球にいながら火星時間で過ごすので他のスタッフと生活時間がズレていくことになります。ただコロナの影響もあってNASAでもテレワークが進んだ結果、意外と苦労しないらしいですよ。

テレワークのような遠隔地での働き方は宇宙の時代にも通じる可能性があるわけですね。

せっかくなので、行きたいワールドがあるので紹介してもいいですか。ちょうどこのワールド制作にも関わっているNikoさんなのですが、ガチガチのシミュレーションをしたワールドがあってすごいので。

ぜひ行きましょう。
ブラックホールにはロマンがいっぱい「Exoplanet Journey」

「Exoplanet Journey」はVSPの誰かがたまたま見つけたものなのですが、星の作り込みがすごいワールドだと団体内で話題になったんですよね。そこで天野ステラさんの解説でイベントを開催したところ、ワールドの作者が参加する大盛り上がりになりました。

パネルからいろいろ星に行けるのですが……


星ではないですが、みんな大好きなブラックホールに行きましょう。

ここまで近づいたら終わりですね(笑)

今映っているブラックホールの形は、実際に撮影した観測データをもとにしています。撮影方法も面白くて、世界各地にある電波望遠鏡をネットワークで繋いで仮想の超巨大電波望遠鏡を作って行いました。

そんなロボットアニメみたいなロマンが実際に行われたの面白すぎませんか?

もちろんブラックホールは肉眼では捉えられないので、観測した電波データをコンピューターで解析した結果が目の前に映っているブラックホールの形です。

ブラックホールの形については、実際に観測したのは先程のFukumaさんの言う通りなのですが、かなり前から考えられている形ではありました。有名なのは2014年に公開された『インターステラー』ですね。

大元はブラックホールの物理現象や観測データをもとにシミュレーションしたものがあります。実際に観測してみたら鮮明に映ったわけではないのですが、たしかにシミュレーションのような形状をしていたわけですね。

ブラックホールといっても、黒い丸の中心部分に点のように本体があるだけなんですよね。周りの黒い部分は光も出ることができないので、ある地点からスパッと何もない空間になってしまいます。言葉としてはイベント・ホライゾン、事象の地平線と呼ばれています。

ブラックホールと垂直に回っている輪っかはどういったものですか。

ブラックホールに吸い込まれる際に加速されたエネルギーが輝く結果、周囲に光の輪(降着円盤)が形成されるからなんですね。

ブラックホールの中に何がありますかね。

それは分からない……

そもそも「主観的」には入れないですよね。

ブラックホールに侵入しようとすると光の速さに到達します。アインシュタインの相対性理論によると、物体は光の速さに近づくほど、物体の感じる時間は遅くなっていきます。

SF作品の王道である浦島太郎理論で出てくる話ですね。

そのとおりです。なので、仮に我々が宇宙船でブラックホールに近づいたとしても、その過程で光の速さになるので主観での時間が限りなく止まってしまうわけです。外から見たら侵入しているように見えても、探索する人たちからすると入っていない状態が続きます。

ブラックホールの中身がブラックボックスなのを考えると、本当にロマンの塊ですね。

今回は宇宙モチーフのワールドを巡っていきましたが、作り込みがすごいワールドばかりでしたね。それこそVSPが制作した宇宙博物館コスモリアも、とんでもないワールドでしたよね。最後に、1人ずつコメントをお願いします。

宇宙って実際に行こうとしても行くのが難しい場所です。だからこそ、ワールドの作り手が自分の中にある宇宙を表現したり、実際に行ってみたい欲求を叶えたいと思ったりするわけです。
もちろん現実にない空想のファンタジーであっても同じことは言えます。ですが、宇宙に関しては現実にあることであり、頑張れば手に届きそうだけども届かないような紙一重感があると思っています。だから自分にある欲求を満たす意味では、VRChatのワールド作りと宇宙って相性がとても良いわけですね。

いつもはテリトリーのワールドやイベントに行くのがほとんどかもしれませんが、たまには宇宙に関するワールドに行ってもらえると嬉しいです。

実はコスモリアに釣られた新参でVRChatを始めたのも2023年の12月と半年程度なんですよ。VSPの目指した活動に憧れて、VRChatにやってきた生き証人みたいな感じです。こうして、VSPに所属したからには今度は供給できる側になりたいなと思いました。

私もVRChatを始めたのは2023年12月なので新参ですよ。

えっそうなの。プレイ歴を考えると馴染んでいるように見えますけども。

昔からいるような顔をしていますけども、新年会から参加した身です。VSPは宇宙に関して詳しい人が多くて話をしていて飽きないです。今回もすごく勉強になりながら聞いていました。

本当に小話から無限に広がりましたからね。今回は本当にありがとうございました。
今回の記事で出てきた話が興味深いと思った人は、天文仮想研究所の公式Xアカウントをフォローしてイベントに参加してみてください。イベントの参加は難しいと思う人は、天文仮想研究所のメンバーで制作したワールド『VR宇宙博物館コスモリア』に行ってみたり、制作者による解説を見たりして楽しむのもいいでしょう。
同じワールドでも見る人によって視点が変わる。当たり前のことではありますが、実際に検証してみるとかなり実感できました。ワールド巡りは1人でもできる遊びではありますが、複数人で来るとそれぞれの視点で楽しめる遊びでもあります。今回は宇宙に詳しい人でしたが、必ずしも知識がないといけないわけではないですので、気軽に楽しんでみてください。

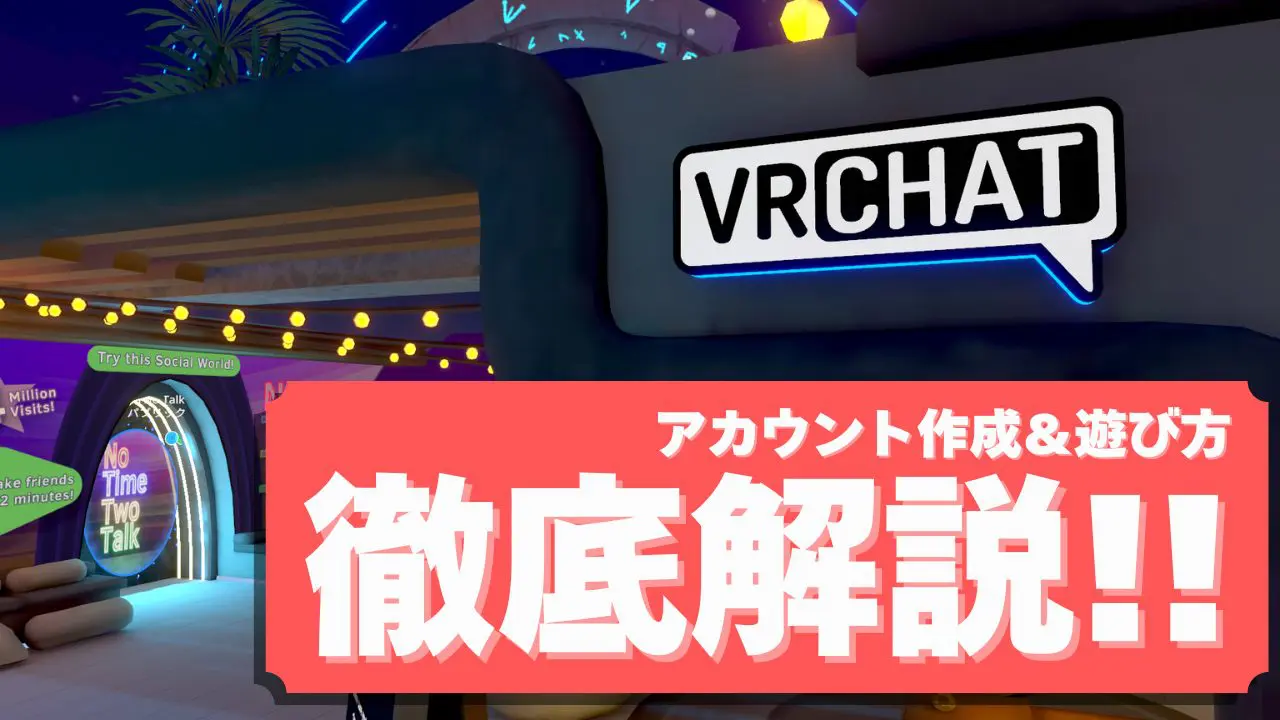

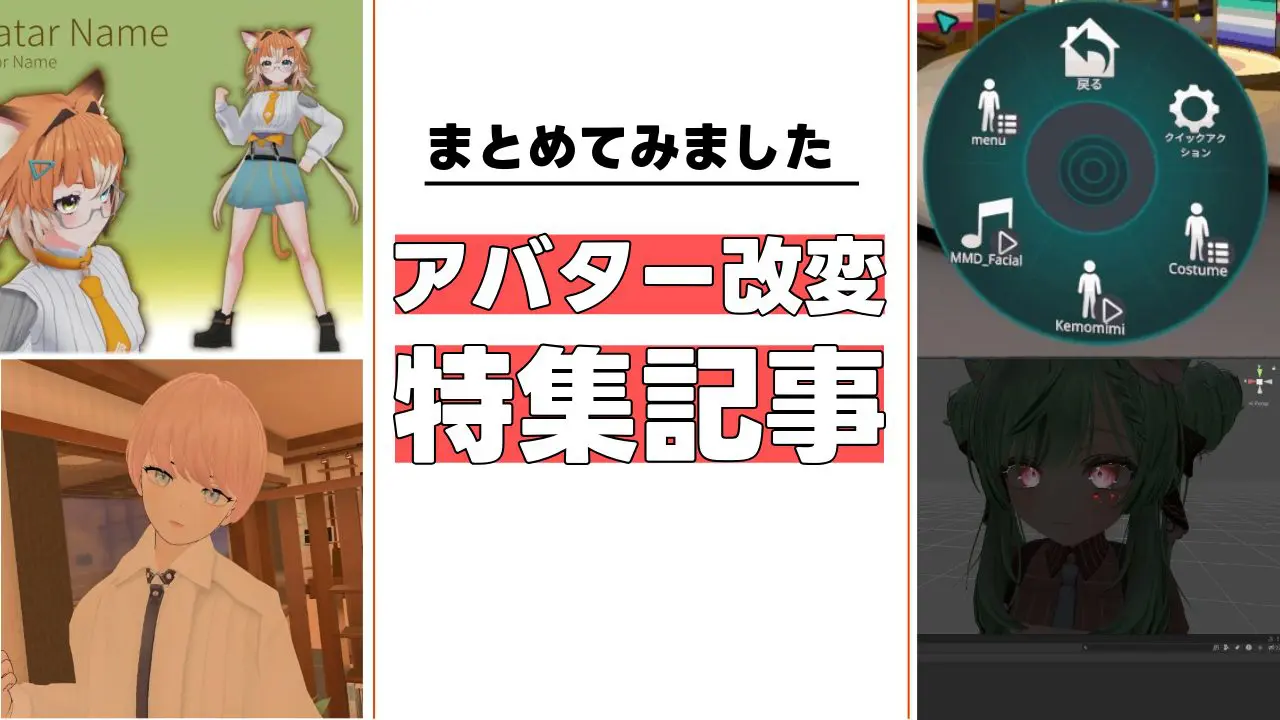








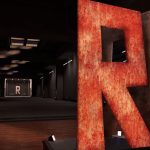

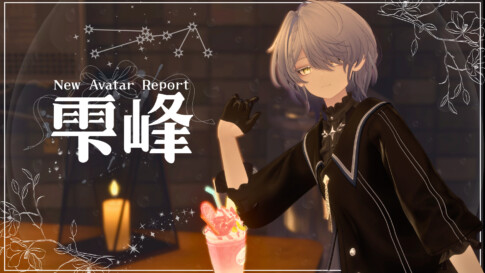


「Generations – Project RAMA 」は別の惑星へ移住するための恒星間宇宙船のワールドですね。エレベーターで降りて居住空間である中心部分に向かっていきます。エレベーターのディスプレイに重力の表示が何か出ていますね。