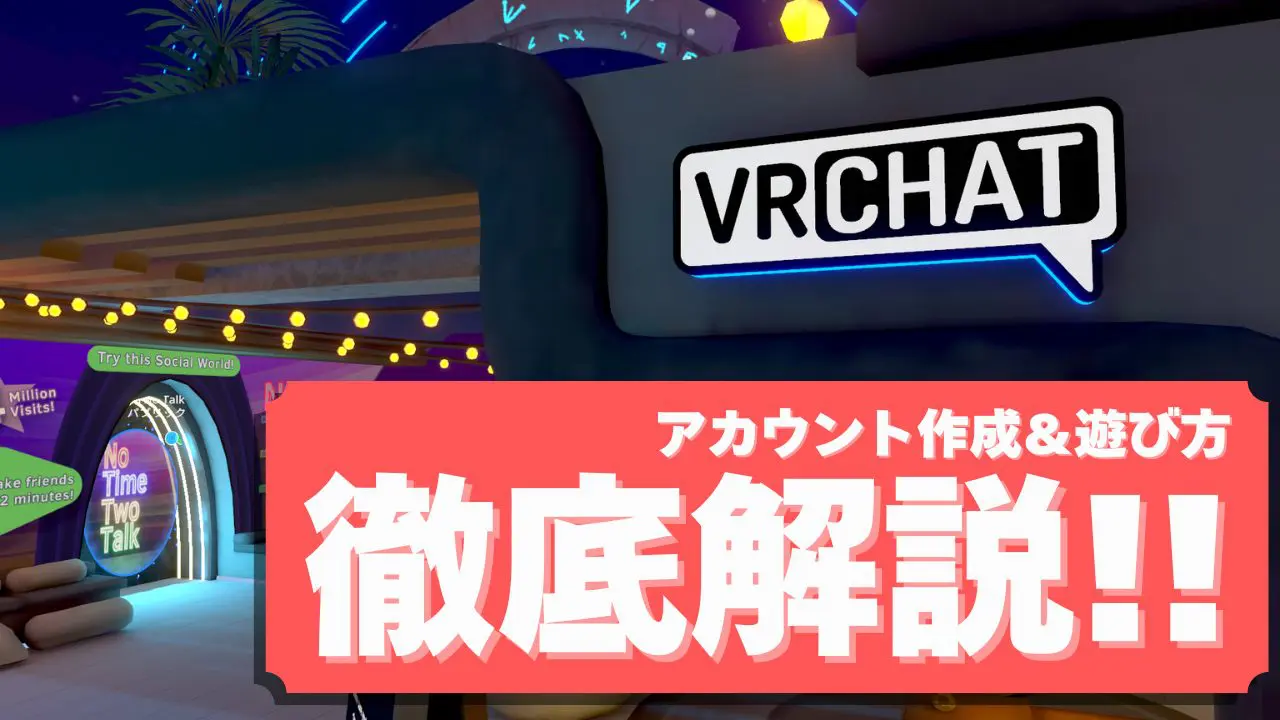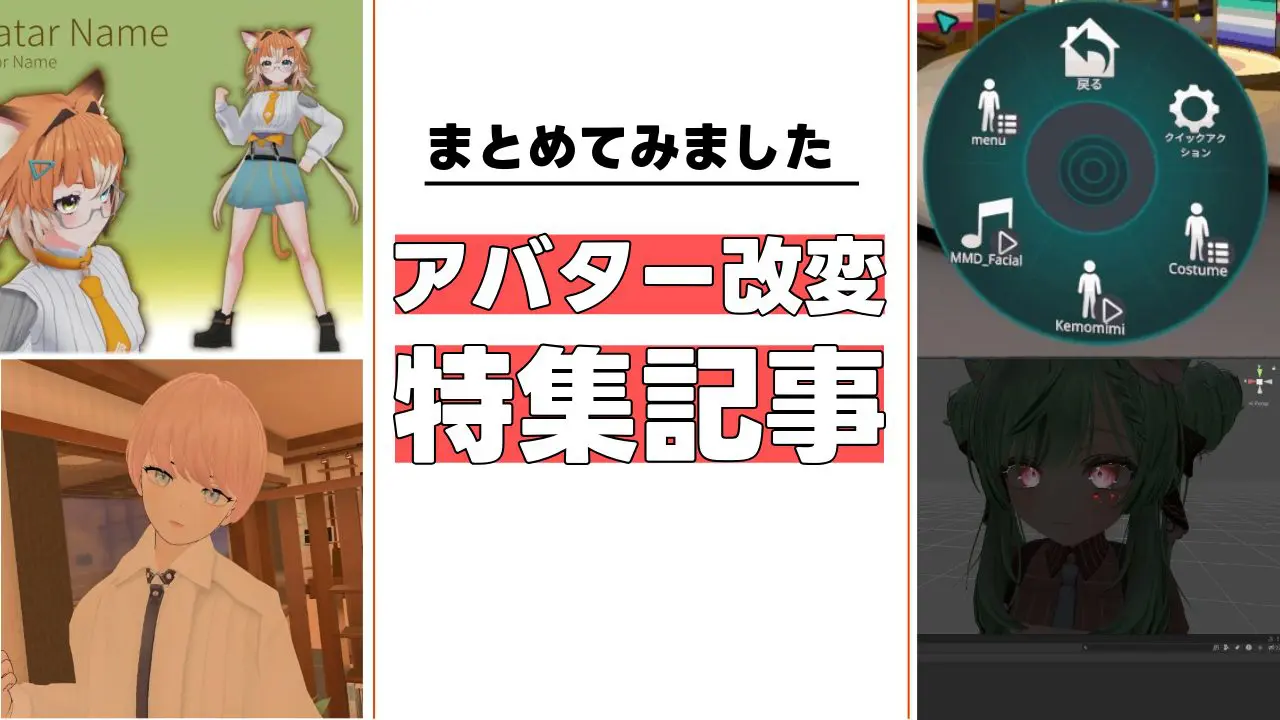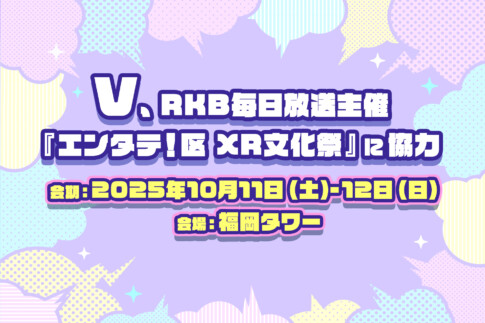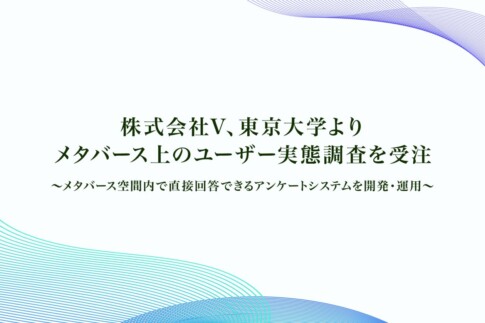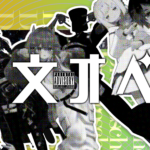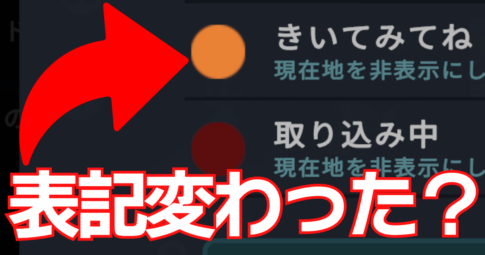私はハッピーエンド主義者である。小説にせよ映画にせよ、フィクションはハッピーエンドで終わってほしいと願っている。悲しいことが多い世の中で、創作の中まで悲しく終わらなくてもいいじゃないか、と思うのである。
ソーシャルVRで活動している劇団「maropi工房」の最新作『走馬灯プランナー』が、3月28日、29日の2日間にわたって上演された。あらすじは以下のとおり。
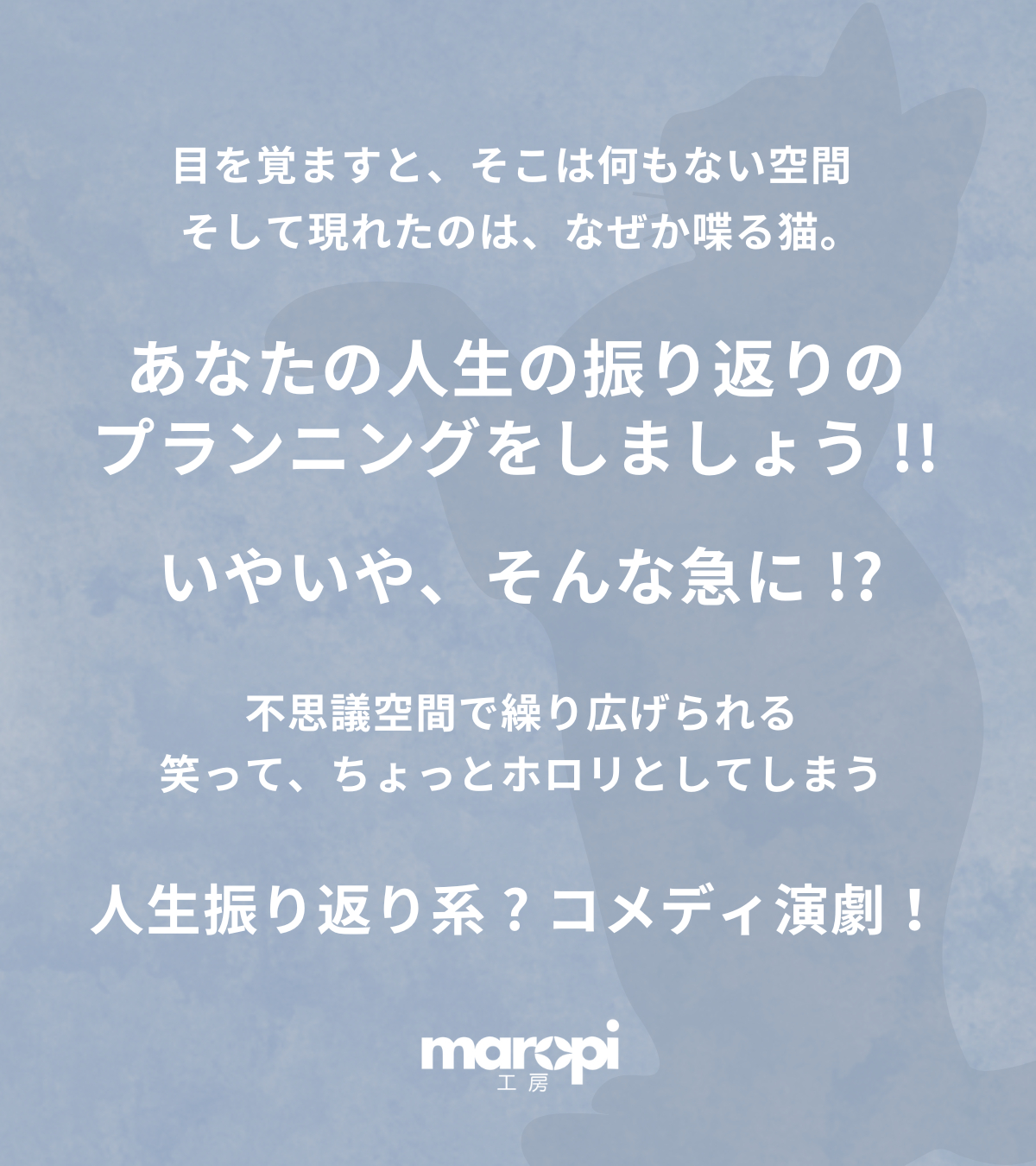
喋る猫、不思議空間、コメディ演劇! 楽しそうな雰囲気が伝わってくる。実際、楽しい公演だった。あらすじに偽りはない。笑えるコミカルなシーンの連続である。でもこの物語、全然ハッピーエンドじゃない!
主人公は最初から死んでいるし、一緒に死んでしまった母親に至っては「フナ虫」になってしまう。観劇後、フナ虫ってどんな見た目だったかなと検索したが、ずっと眺めていたいものではなかった。
では、私にとって『走馬灯プランナー』は駄作だったのか。
いや。本作は、“ハッピーエンドであってはいけなかった” のだ。
※初日公演のアーカイブ
ハッピーエンドになりそうな伏線は全部つぶしておきますね
公演が始まると、まず、慌てた様子の主人公「青井」が登場する。見ると、足が透けている。

タイトルに「走馬灯」が含まれているので、「死」がテーマなのだろう。だから、足が透けているということは、死にかけているという暗示かもしれない。ハッピーエンド主義者として妄想が膨らむ。“最後に息を吹き返し、これからの人生は悔いなく生きていくぜ” という展開が見える!
しかし、そこへ現れた、プランナーと名乗る猫が言う。
「非常に申し上げにくいのですが、青井様はもう既にお亡くなりになられてまして」。
それだけでなく、トラックと衝突したせいで “ちょっとわかんなくなっちゃってる” 青井の姿を本人に見せて、言い放つ。「ね、さすがに死んでるでしょ」。
……猫めっ。私のハッピーエンドを返せ!

さて、そもそも「走馬灯プランナー」とは何なのだろうか。
猫の説明によると、それはどうやら、“人生のどの場面を走馬灯として見るかを故人が自分で決められるようサポートする役職” のことらしい。たしかに、ランダムよりは、自分で決められるほうがいい。
そして猫は言う。「幸福度が高いポイント3つをおまとめする幸福プランをおすすめしておりますがいかがでしょうか」。
こうして青井は、自分の人生の中で特に幸福だった時を振り返っていくことになる。
「大学入学」「漫才コンビ結成」「お笑い賞レースの舞台」である。

振り返りを通して分かってくるのは、青井は親の反対を押し切ってお笑い芸人になったということ、そして、お笑い芸人の道を選んだことを後悔しているということである。だからなのか、“自分が幸福だった時トップ3” を見ているというのに、本人はどこかピンと来ていない。
人生を振り返った後、猫から「(最近の走馬灯では)人生の選択肢を変えちゃう、みたいなことはできますね」と提案され、青井は、「大学の頃に戻って、お笑いサークルに入らない選択した自分を知りたい」と答える。そして、「こっちの人生にして」と。

しかしその後、青井は、母が、“息子が芸人になると報告しに来た時、反対せずに応援する” という走馬灯にしたことを知る。
沈黙の後、青井は先の決定を撤回し、「演出とか、全部なくていいや」とつぶやく。「そのままで、そのままがいいんだよ」と——。
ストーリーを簡単にまとめると、主人公は過去を後悔していて、ある意味で過去を変えるチャンスが来るが、最終的には過去を受け入れる。
これだけ見れば実にハッピーエンドだ。しかし、今作において、主人公に未来はない。過去を受け入れて前を見て生きていくことができない。母親に何かを伝えることも、もうできない。
だからこそ、その切なさは、観客への問いかけとして強く響く。
——これを観ている君は生きているんだ。未来があるんだよ。
——君は過去を、そして今を、どう受け止める? これからどうしていきたい?
この物語が、“実は生きてましたエンド” だったとしたら、ここまで心に迫るものはなかったように思う。そういうわけで、本作はハッピーエンドであってはいけなかった。すっきりした気持ちで終わってはいけなかった。これを観た私たちは、そのやるせなさを、自分自身の人生にぶつけなくてはいけない。そう感じた。
この猫、実に不謹慎
観劇していて思ったことがある。この猫、やたら褒めるし、やたら寄り添うな、と。
褒めたり寄り添ったりするのはいいことなのになぜそう思うのか、最初は自分でもよく分からなかった。でも後から気づいた。この猫、言動がひたすら不謹慎なのだ。それで、親切と不謹慎が同時に存在することに違和感を覚えたのだろう。
例えば、自分が死んだという状況を受け入れられず戸惑っている青井に、「お気持ちお察しします」と声をかけておきながら、プランニングの説明を淡々と続ける。
「俺の母親ってどうなったかわかる?」と尋ねられると、事故でぐちゃぐちゃになっている母親の姿をちゅうちょなく見せつける。
そして、「お母さまフナ虫になりました」と、なんだか楽しそうに言う。
しまいには青井にも、「お母様もフナ虫になられたわけですし、そこは私も頑張らせていただいて、一緒にフナ虫になるように調整させていただくこともできます」なんて提案する。
この猫やばい。不謹慎というか、心がない。AIみたい。

ただ、皮肉なことに、青井が自分の過去を受け入れられたのは、このやばい猫のおかげだとも思うのだ。
青井は、猫からいろいろと質問され、自分の気持ちを言語化することで、本心に気づき、悪くない人生だったのかもしれないと思うことができた。
この猫、やばいくせになかなかいいことを言うのである。
漫才コンビ結成の場面で青井が、「授業すっぽかしてネタ考えたり、何しに大学行ってたんだって話だよね」と自分を卑下すると、「いいじゃないですか、そんなに熱中できることが見つかって」と褒める。「素晴らしい、ほんとの自分!夢を見つけた感じですね!」と。
「そんないいもんでもない気がするけど」という後ろ向きな発言に対しても、「でも、この時楽しかったことに間違いはないってことですよね」と強く肯定する。
自分で自分のことをここまで肯定するのって難しい。
自分では気づきにくいことがある。何者かになりたいとか、他人と比べると自分は大したことがないとか、そんなふうに思うことがあるかもしれない。でも、ほかの人からしたら、自分の人生だってうらやましいものなのかもしれない。自分が思っているよりも、自分は悪くない日々を送っているのかもしれない。

お笑いサークルに入らないifストーリーを見た青井が、「あの時勘違いして挑戦なんかしなければ、こんな人生だったのか」と口にすると、「実際はこっちはこっちでここまでに色々とご苦労とか、後悔されていることもあるかとは思いますが」と猫は言う。
たぶんこれが真実だ。華やかに見える他人の人生も、本当のところはどうなのかは分からない。
自分一人だと気づけないことがある。それと同時に、他人の声に振り回され過ぎるのも虚しいことだ。最後に答えを出すのは、自分を受け入れるのは、自分にしかできない。いつだって、決定するのは自分なのだ。
そのことが、最後のシーンから伝わってくる。過去の自分と今の自分のセリフが交差するシーンは鳥肌ものである。

これは演劇なのか?
観劇後に、不思議な疑問がわいてきた。あれ、自分は何を観ていたんだっけ。
このレポートを書くためにアーカイブを観たが、再び、なんだこれ?と思った。いまだに上手く言語化ができない。私が観たのは、演劇だったのか?
入場すると、そこは小さくも大きくもない、四角い空間であった。観客はどこから観てもいいし、実際、舞台はぐるっと360度である。いつしか時計の針の音が聞こえてきて、視界が暗くなり、気づけば始まっている。観終わってからようやく、席に座らない演劇だったなと気づいた。
観劇用のアバターはふわふわ浮く小さい球体であり、ほかの観客の存在があまり気にならない。自分一人のために上演されているような、劇の中に入り込んだような、そんな感覚。
ひとことで言えば、没入感が高かった。主人公に感情移入できるとか、そういうレベルの没入感ではない。一人の人を看取った。そう思ったのだ。

脚本、演技、舞台、演出、すべてが見事にかみ合っていた。この良さを100%味わうには、VRで観るのが一番だ。今回現地に行けなかったという方は、次回作はぜひ予約して観に行ってほしい。
最後に、このレポートで書いたことはいち観客の感想に過ぎないという点を付け加えておく。この作品を観て何を感じ、そしてどうするかもまた、一人一人違う。
私としては、こいつずっと的外れなことを言ってるな、とmaropi工房の皆様から冷たい目で見られていないことを願うばかりである。
※千秋楽公演のアーカイブ
●参考リンク
・maropi工房 公式X